
中 山 道
|
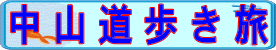 |
26 芦田宿から長久保宿へ 歩行地 図 |
| 仲居-芦田中央-松並木-笠取峠-松尾神社-長久保 6.3 km |
|
26芦田宿
。慶長2年に街道の南側より移転してきて形成された。望月宿より小さな宿であるが、難所であった笠取峠の東の入口にあるので、休憩する旅人が多かった。和宮もここの本陣で休憩している。昭和52年の火事で脇本陣のうち1軒が焼失している。
本陣1 脇本陣2 旅籠6 |
  2008年7月5日望月宿より続く 2008年7月5日望月宿より続く
■芦田宿~松並木
●芦田宿入口
当時の宿場は小さな芦田川を渡った「仲居」交差点付近から始まっていたが、交差点角に現在の常夜燈が設置されている。また宿内の通りには「芦田宿」と書かれた昔風の●「街灯」が設置されている。10:20 |
  ●町並み ●町並み
現在の芦田宿は「立科町」の中心として栄え、旧道左手には立派な「立科町役場」も見られるが小さな宿場だったし、人出があまりなかった。
●本陣跡
右手に立派な門構えの屋敷が見えるが、本陣だった●「土屋家本陣跡」で、当時の本陣は「問屋」も兼ねていたと言わる。見学は予約が必要らしく、門から覗いただけだったが、建物は寛政12年(1800)のものだそうで、「県宝」の指定になっている。説明板 |
  ●脇本陣 ●脇本陣
この本陣向かい側には脇本陣の一つがあったが、今は小さな「脇本陣跡」碑が立てられているだけ。
もう1軒の脇本陣跡が本陣跡から少し歩いた左手に残っていて、ここは
●脇本陣、もう一軒の方の、脇本陣で、「山浦家」と呼ばれ、当時は「庄屋」も兼ねていたという。
10:40 |
  山浦家向かいには●「酢屋茂」という屋号の古い家が見られるが、ここは昔から味噌や醤油を造っていたという。 山浦家向かいには●「酢屋茂」という屋号の古い家が見られるが、ここは昔から味噌や醤油を造っていたという。
この先にも「軒うだつ」の残っている古い家が数軒見られるが、その中の●「金丸土屋旅館」は現在も旅館を営業しているが、元は旅籠屋をやっていたという。
芦田宿はこの先の「芦田」の信号がある交差点が宿はずれだった。 |
  ■松並木~笠取峠 ■松並木~笠取峠
●笠取峠の松並木
宿場を出る途中には、道祖神などがあり、先は再び急な上り坂で、上り切ると「芦田宿入口」碑があって国道に突き当たる。ここで国道を横切り、●「新しい常夜灯」の置かれている脇を過ぎると、見事な「松並木」が目に飛び込んでくる。これが江戸時代から有名だった「笠取峠の松並木」で、現在ここは国の「天然記念物」にも指定されている。 11:05 |
  ●松並木風景 ●松並木風景
慶長7年1602)、幕府から拝領した「赤松」753本を植えたのがここの始まりで、残った松並木は東海道御油の松並木と並ぶ見事なものだという。 当時の松並木は笠取峠までの15丁(1600m)ほどに植えられていたが、今も両側約1キロにわたって残り、地元の人々らに愛されている。途中「道祖神」や「歌碑」などが沢山並んでいた。松並木説明板 |
  やがて松並木は●国道に合流し、峠まできつい登り道が続く。中山道は山道で坂がとても多いが、ここもいささかつらく、昔の旅人は雨が降れば、ツルツルする坂を上り下りすることは本当に大変だと痛感する。右手にあるという「笠取峠の一里塚」は気がつかず通過してしまった。 やがて松並木は●国道に合流し、峠まできつい登り道が続く。中山道は山道で坂がとても多いが、ここもいささかつらく、昔の旅人は雨が降れば、ツルツルする坂を上り下りすることは本当に大変だと痛感する。右手にあるという「笠取峠の一里塚」は気がつかず通過してしまった。
頂上をやっと越える。このあたりは国道の改修で旧道はほとんど消えている。右手に別荘地入口があり、●「笠取峠碑」や「常夜灯」が置かれている。 11:45 |
  ■笠取峠~長久保宿 ■笠取峠~長久保宿
国道を下って行く。右手壁に「立場」のタイル絵など掛けられている。さらに下ると「中山道」の標識が置かれているが、ここからは国道を離れ、●右手に残った旧国道部分に入って行く。
「旧中山道」はこの●旧国道ではなく、つづら折りの旧国道を直線的に横切って長久保宿の方向へ下っていっている。通行不能なので、ここは旧国道を旧中山道のつもりと思って歩くしかない。(後で調べた所、国道と旧国道の間に「中山道元道」というのがあり、そこが旧街道のようでした。後の祭りで気がつかなかった) 11:55 |
  旧国道自体もつづら折りの下り坂だが、途中何ケ所かに「中部北陸自然歩道標識」が置かれているので迷うことはない。 旧国道自体もつづら折りの下り坂だが、途中何ケ所かに「中部北陸自然歩道標識」が置かれているので迷うことはない。
何度か右往左往して行くと、左側に●馬頭観世音と野仏がちょこんと鎮座していらっしゃるので、旧道の名残か移設されたものかと思った。旧国道をなおも●下り続け、国道と合流したりして坂を下り続ける。
12:15 |
  最後に●上五十鈴川橋を渡り、道なりに右にカーブして下るところで、松尾神社を右下に見て、ここから下り坂を下りて行くと「長久保宿」と書いた標柱が見えてくる。神社脇へ続く旧中山道の道筋も残っているようで、狭い石段の様な所を、下りていくと、神社へ出られるが、ここは●広い道を行っておいた。 最後に●上五十鈴川橋を渡り、道なりに右にカーブして下るところで、松尾神社を右下に見て、ここから下り坂を下りて行くと「長久保宿」と書いた標柱が見えてくる。神社脇へ続く旧中山道の道筋も残っているようで、狭い石段の様な所を、下りていくと、神社へ出られるが、ここは●広い道を行っておいた。
長久保宿へ続く 12:25 |
|