
中 山 道
|
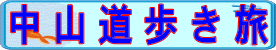 |
20 追分宿から小田井宿へ 歩行地図 |
| 追分宿-文学記念館-分去れ-西軽病院-御代田-荒町-小田井 5.9km |
|
20追分宿
ここでの「追分」の意味は平安時代の官道と北上州道が分かれ、また中山道と北国街道との分岐点でもあるという新旧二つの地名に由来する。中山道や北国街道からの大名がこの宿を通過し、非常に繁栄した。また天保9年には「貫目改所」が設けられた。明治時代の信越線開通により急速におとろえたが、堀辰雄ら文士や学者などの別荘も増え、軽井沢の文教地区などとも呼ばれて賑わいを見せるようになっている。民謡の追分節の発祥の地でもある
本陣1 脇本陣2 旅籠35 |
  2008年7月5日 沓掛宿に続く 2008年7月5日 沓掛宿に続く
■追分~分去れ
追分の一里塚跡から旧道に入ると右手に見えてくるのは郷土館」で、ここには街道の資料がたくさん展示されている。入り口にも巨大な●馬頭観音碑が立てられている。寛政6年の碑で高さ3mもある。なお館aの中では「追分節」が聴ける。また隣の浅間神社の境内には「●追分節」発祥の碑」というのも立っている。馬子の仕事唄である馬子唄に三味線が入り、座敷唄に発展したものが追分節ということだそうだ。10:55 |
  ●浅間神社 ●浅間神社
現在の本殿は室町時代の建築といわれるが、例により囲われていて見ることが難しい。境内は広くなかなか立派は風情である。
●浅間神社の芭蕉句碑 ここには
ふき飛す石も浅間の野分哉
と彫られた大きな「芭蕉句碑」が置かれている。句碑はとても巨大な自然石でできていて、寛政5年の建立
11:25 |
  浅間神社を出てしばらく歩くと「昇進川」を渡る。この川を渡ると●旧宿場跡。賑やかなな宿場だった。左手には堀辰雄 記念館が作られているが、その門に使われているのが、●「追分宿本陣の裏門」である。本陣は代々「土屋市左衛門」が世襲した。明治になり本陣の機能を失い、他家へ移築された。裏門はこの記念館の門として使われている。これでも裏門にすぎなく、本来の表門は遙かに立派なことが想像される 11:30 浅間神社を出てしばらく歩くと「昇進川」を渡る。この川を渡ると●旧宿場跡。賑やかなな宿場だった。左手には堀辰雄 記念館が作られているが、その門に使われているのが、●「追分宿本陣の裏門」である。本陣は代々「土屋市左衛門」が世襲した。明治になり本陣の機能を失い、他家へ移築された。裏門はこの記念館の門として使われている。これでも裏門にすぎなく、本来の表門は遙かに立派なことが想像される 11:30 |
  ●脇本陣」(油屋旅館) ●脇本陣」(油屋旅館)
記念館の向かいに見られるのが脇本陣であった「油屋」旅館。。建物は昭和26に焼失し、昔と反対側へ他から移築したものという。ここは今も旅館を営んでいる。隣の古い家は●「現金屋」と呼ばれていた店で、骨董品がたくさんある。またその隣が本陣を勤めた、「土屋家」があったという。またその先には高札場跡も見られる。 11:50 |
  宿場はその後●国道に出てしまうが、合流する辺りは「枡型」に曲がっていた所で、土手が築かれて、入口の備えになっていた。ここには古い●「つがるや」の建物が残っている。ここは昔の茶屋で、枡形の近くにあったので、「枡形の茶屋」と呼ばれている。今でもほぼ原型を保っているそうで、保存をする必要があるように思う。12:00 宿場はその後●国道に出てしまうが、合流する辺りは「枡型」に曲がっていた所で、土手が築かれて、入口の備えになっていた。ここには古い●「つがるや」の建物が残っている。ここは昔の茶屋で、枡形の近くにあったので、「枡形の茶屋」と呼ばれている。今でもほぼ原型を保っているそうで、保存をする必要があるように思う。12:00 |
  ●分去れ ●分去れ
国道に合流するとすぐ先に見えてくるのが「追分」発祥地とも言うべき「分去れ」で、今も当時のままに「常夜灯」を初めとして多くの「道標や石碑」が置かれている。一番前にあるのが、
●道標で右側に「従是 中山道」左側に「従是 北国街道」と刻まれている。江戸から来ると右側の道が北国街道になる。北国街道は善光寺まで18里ほどだった。
12:05 |
  ■分去れ~御代田 ■分去れ~御代田
さて、旧中山道は分去れから国道左手に移ってしまう。左手に入ると面白い建物があった。
●中山道69次資料館
入場料500円で、民間の施設のようだが、中山道の資料がそろっている。街道脇に、江戸から京都までの、超ミニサイズの山あり、谷ありの●「69次の遊歩道」が作られている。なんか子供だましのような感じがする |
  この先の道路は●●「追分原」といわれて、昔のままの殺風景な雰囲気が残っている。建物の周りに浅間山の噴火石が使われていることが多い。当時この付近は「浅間山噴火」の影響が大きく、火山灰が積もって、不毛の地だったという。ただ落葉松だけは育ち、ちょうど「英泉」が「浅間山眺望」と題して残した絵もこの付近ではないかと言われている。12:35 この先の道路は●●「追分原」といわれて、昔のままの殺風景な雰囲気が残っている。建物の周りに浅間山の噴火石が使われていることが多い。当時この付近は「浅間山噴火」の影響が大きく、火山灰が積もって、不毛の地だったという。ただ落葉松だけは育ち、ちょうど「英泉」が「浅間山眺望」と題して残した絵もこの付近ではないかと言われている。12:35 |
  御代田の一里塚 御代田の一里塚
ずっと緩い下り坂が続いていて、バス停「桜ヶ丘」の先、少し歩くと、看板が出ていて、右手奥へ行った所に「御代田の一里塚」と呼ばれている、見事な一里塚が見えてくる。ここは中山道改修以前の一里塚で、現在の道より奥まった所に作られている。●西塚、東塚とも保存状態も良く貴重な存在です。12:50 |
  ■御代田~小田井 ■御代田~小田井
一里塚跡を出ると中山道は「しなの鉄道」に突き当たってしまうが、ここには●地下道があり、地下道を潜って行く。すぐ右には御代田駅があり。この辺りは人家や商店も多い。潜って右手へ行き、左手に入る。左側には旧家らしき家があったようだけど、取り壊し工事の最中だった。旧道はやがてバス停「荒町上町」を通過し、左手に●長い板塀のある名主のような家がある。 |
 小田井宿入口 小田井宿入口
旧道はバス停「荒町上町」、「荒町」と過ぎて、県道137号にぶつかる。ここが「小田井上宿」信号で、小田井宿の入口になる。信号手前の右側にも、●御嶽山、八海山やらの石碑が沢山並んでいた。
小田井宿へ続く 13:15 |
|